


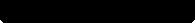
|
LossTime 21/02/02 須坂アートパークにお雛様を見に行く

今日は節分。通常節分は2月3日ですが、今年は2月2日が節分です。
節分が2月2日になるのは1897(明治30)年以来124年ぶりのことなのだそうです。節分はその名の通り、季節の分かれ目。立春の前日となるので立春がずれると節分もずれるのだそうです。
そんな今日、雛祭りにはちょっと早いけど、須坂アートパークに「三十段飾り千体の雛祭り」を見に行ってきました。暇つぶしです。
小雪が舞う肌寒い一日。さすがに来場者は私だけで、密になることはありませんでした。 |
三十段飾りの雛人形
◆ 江戸時代 ◆
享保年間(1716〜1736)頃に最も流行したとされる座り雛。
総じて大型のものが多く、衣装も金襴や錦などを使い、面長で神秘的な表情をしています。 |
◆ 明治時代(左) 大正時代(右) ◆
安永年間(1772〜1781)頃に江戸で生まれたとされる雛人形。
古今雛(こきんびな)と呼ばれ、明治以降から現代にまで引き継がれています。古今雛は比較的裕福な家庭で送られるものであったため、大型で高価な布地を使っているのが特徴です。 |
◆ 昭和時代 ◆
昭和30年以降の高度成長期は日本も豊かになり、雛人形も大型で豪華なものが作られるようになりました。
バブル期は金色の刺繍や豪華な色彩のものが多く、派手な雛が多く作られています。 |
◆ 平成時代 ◆
平成のお雛さまには “核家族化” や “住宅事情” が垣間見えます。
アパート・マンション暮らしという住宅事情から、これまで一般的であった7段飾りから、親王飾り(男雛女雛だけの雛飾り)が主流になってきました。 |
|
21/02/06 練習試合(45x3)
清水 1 - 1 磐田 |
 |
前回の練習試合相模原戦は結果すら公開されなかったが、なぜか磐田戦は結果だけでなくメンバーまで公表された。ただ、ファンサービスの観点では、これが普通と思うが
… 。
スコアが動いたのは3本目なので、90分ではスコアレスドロー。現時点での清水はJ2磐田と互角と考えるべきだろう。まぁ、失点しなかったのは良かったかなぁ。
先制した磐田の後藤選手は15歳の中学生なんだとか。スーパー中学生誕生か!? ゴン二世になれるか!? |
|
21/02/08
5,000人 or 50% |
 |
今季もFUJI XEROX SUPER CUPが開催される。カードは天皇杯決勝と同じ川崎 vs G大阪。キックオフは2月20日 13:35、場所は埼玉スタジアム2002。ただ、チケットはいまだに発売されていない。
これは緊急事態宣言が影響しているのだろう。埼玉県は(神奈川県も大阪府も)緊急事態宣言の対象なのでイベントの上限は5,000人、かつ、50%以下。緊急事態宣言が解除されれば50%が上限になるので、埼スタなら約30,000人になる。収益面でこの差は大きい。
新規感染者数を見ると状況はかなり良くなってきているが、待っていても首相は解除の判断しそうもないので早くチケット発売したら! |
|
21/02/09 練習試合(45x3)
清水 4 - 4 松本 |
 |
“苦手” J2松本山雅に練習試合でも勝てず。山雅は数日前の広島との練習試合で 1 - 8 で負けていたため大勝を期待していただけに、ちょっと
… いや、かなり残念な結果。
まぁ、90分では 4 - 1 なので良かったことにしましょう。鈴木と新戦力サンタナが得点したしね。 |
|
21/02/10
浦和 柏木と杉本が規律違反 |
 |
浦和の柏木陽介、杉本健勇が沖縄トレーニングキャンプ中にクラブの規律に反する行為があったことが公式HPで公表された。二人はクラブが禁止している外食をしたとのこと。
別にこんなこと公表してくれなくて良いのになぁ … と私は思う。 |
|
21/02/13 練習試合
清水 vs 藤枝、東京V |
 |
今日はJ3藤枝とJ2東京Vとの練習試合があったはずだが、またもや結果も非公開。どうやら試合はアイスタ日本平で行ったようだ。
J開幕まであと2週間。チームの状況はどうなんだろう … 気にしても仕方ないが、気になる。 |
|
21/02/14
エウシーニョ 合流か!? |
 |
いつのまにか公式HPに写真付きの選手・スタッフの一覧が掲示されている。写真なし “COMING SOON” なのは新戦力のウィリアム マテウスのみ。来日未定で心配されていたエウシーニョはちゃんと写真付きで紹介されている。
ということはエウシーニョは既にチームに合流しているのか!? 重要な戦力なだけに、ぜひ開幕に間に合ってほしい。 |
|
21/02/15
必勝祈願は21日 |
 |
新型コロナウィルスの影響で延期になっていた必勝祈願、出陣式は21日(日)に行うことになった。
見学不可ならわざわざ日曜日に行う必要はないような … 。 |
|
21/02/17
規律違反の浦和 柏木が退団 |
 |
沖縄キャンプ中に規律違反が発覚した浦和の柏木。内容が外食だけに「その程度のことで … 」と思っていたら、柏木は規律違反の常習犯。ロドリゲス新監督も「受入れられない」と激怒している模様。契約解除ではなく移籍、しかも移籍までの練習場所は提供するというのはクラブの温情だろう。
柏木にはしっかり反省し、今まで以上に活躍してほしい。ただし、清水戦以外で。 |
|
21/02/19
茨城のくせに生意気だぞ〜! |
 |
「天気が良かったら27日の開幕 鹿島戦を観戦に行こう」などと思っていたら、一般販売分のチケットが即完売になってしまった。これじゃあ行けないじゃん!?
さて?稼働率がかなり低いカシマスタジアムが完売とは、なぜ??? 正解は清水の公式HPに掲載された情報。なんと、茨城県は独自の緊急事態宣言が発令されていてイベントの収容人数はMax5,000人。5,000人ならさすがのカシマスタジアムでも売切れるのも納得。
しかし … 県独自の緊急事態宣言を発令するとは “茨城のくせに生意気だぞ〜!” |
|
21/02/20 FXSC
川崎 3 - 2 G大阪 |
 |
| またしても、あと一歩及ばなかったG大阪。残念だが、とてつもなく遠い一歩のような気がする。今季も川崎が勝ち続けそうだ。 |
|
練習試合
清水 vs ? |
 |
| 今日は練習試合が組まれていたが、対戦相手を含め全てが非公開。多分写真も掲示されないんだろうなぁ。 |
|
21/02/21
今年もキャプテン三人体制 |
 |
今季もキャプテン三人体制。キャプテン4年目の竹内と新戦力の権田、鈴木だ。
竹内には “生え抜き” の意地を見せてほしいものだ。キャプテンから外れた金子、立田も同様、ブラジル人や新戦力をのさばらせてはいけない。 |
|
|


















